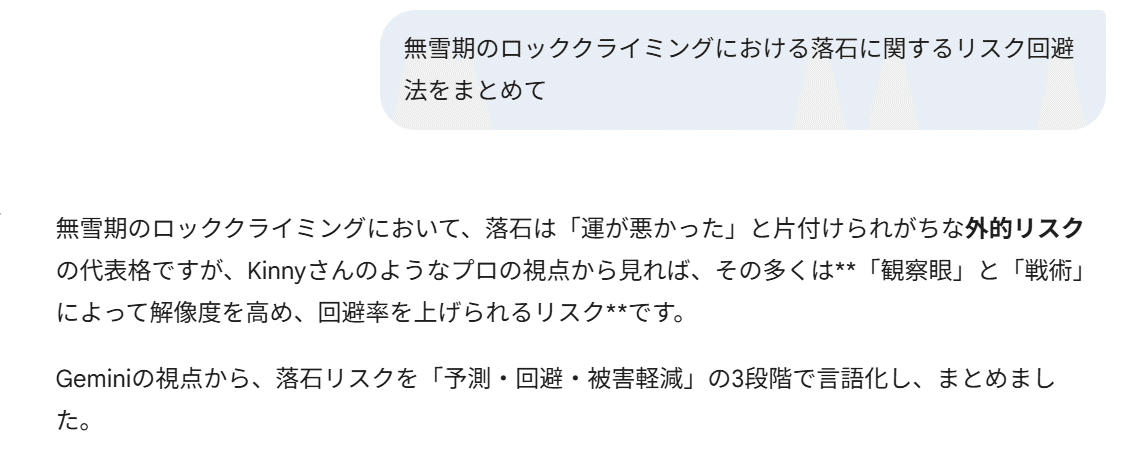こんにちは。積雪期ガイドステージ2保持者のKinnyです。
私は山梨県に夫の仕事の都合で転勤になったので、そこで登山を始めました。雪の山からスタートして、アイスクライミングへ進み、そこまでは自分で習得し、その後沢登りへ、そして、アルパインクライミングへ進み、最後はフリークライミングで、ある程度登れるようになり、海外で登り、暇だったので、ガイド資格を取得しました。
そのプロセスで、印象に残る山岳遭難がいくつかありました。
1つ目は、誰もが知る、トムラウシ。
2つ目は、祖母谷から清水岳での遭難。
3つ目は、学習院大学の阿弥陀北稜。
4つ目は、祝子川です。
トムラウシは、山業界にいる人は誰もが知る遭難で、要するに衣類の調節をしなかったのです。ここは詳述された書籍もあるので飛ばしますが、持っていても服を着ない、指示待ち人間のミスは、年配の人の遭難に多いです。
清水岳の遭難は、私は現地で遭対協の人が批判するのを現場で聞きました。そもそも北アを九州の登山ガイドがガイドしており、現地の人がとらないルート取りでした。東京をガイドしてほしい時に、大阪の人に頼みます?お門違いですよね。それが登山だと分からなくなります。不思議ですね。
学習院大学の遭難については、一家言あります。というのは、私のホームグランドの山が八ヶ岳なのです。登山を学んだ時に、私を指導教官をやってくれた人も八ヶ岳の遭対協だったので、阿弥陀北稜くらいは誰でも登れるようになってほしいと思っています。とくにアルパインをやる人は、入門ルートです。
大昔に書いた阿弥陀北稜の遭難についての記事。https://stps2snwmt.blogspot.com/2015/10/blog-post_12.html
大学山岳部には特有の危うさがあります。
しかし、阿弥陀北稜は決して危険なルートでもなく、簡単でした。私は単独初見で自分で行っています。39歳で雪山をスタートし、44の時に行きました。しかも、私は女性です。つまり難しい山ではないということです。
祝子川については、エイト環ではなくATCガイドを使って確保し、おぼれたということらしい(推定)ので、沢登教室の初日に言われるような基礎的なことをさぼっていたと思われます。事故報告書は公開されていないです。そもそも、ゴルジュに2名って非常識です。沢登りは、数ある登山形態の中でも事故ったときのリスクが高いです。携帯電話が入らないのです。沢は。難易度によらず。私は一人でも沢に行きますが、ゴルジュなどない1級の沢です。
それぞれ、
トムラウシは、ハイキングレベルの人のリスクの具現化
清水岳は、縦走する人のリスクの具現化
阿弥陀北稜は、アルパインクライミング入門者のリスクの具現化
祝子川は、沢登り中の事故の具現化
ですが、自己責任と言えるのは、トムラウシまでです。
共通して言えることが心理学的なリスクです。
私は大変慎重な性格らしく、その私からしたら、わざとに事故りに行っているとしか思えない内容です。
わざと事故りに行っている度合いをレーティングすると
清水岳は、★★
阿弥陀北稜は、★★★
祝子川は、★★★★★★★★★★★
って感じです。
最後の祝子川の2名での事故など、「行きましょう」とお誘いを受けたら、速攻でお断りできるようなお誘いです。事故る前からわかる。
清水岳は、ルート取りが悪く、小屋で停滞をすべき時に行ってしまったので判断のミスです。しっかりしたローカルガイドなら起きない。
阿弥陀北稜に関しては、リスクが分かりにくいので、指導者が必要だったのでしょう。
阿弥陀北稜は、”下山に習熟してから登れ”というのが一般的なアドバイスですが、この言葉の意味が分かる人が現代登山者の中にそもそもいないのです。
私は阿弥陀岳の一般ルートは当然のことながら、御小屋尾根、阿弥陀中央稜と北稜以下の難度のルートは、全部やってから行っています。無論、コンパスでの東西南北の把握もできるようになっているというのは、ハイキングの時点で習得済みが前提です。
阿弥陀岳は多くのルートがある。つまり一つのピークから派生している尾根が多いという意味ですので、降りる方向の角度をほんの少し間違えただけで全然違う場所に降りてしまいます。北稜のほか、南稜、北西稜もあります。広河原沢や摩利支天大滝という氷のルートもあり、山の全体像を知っていないと、遭難につながります。
そうしたことを知らない人で、昨今はルートコレクター的に来る人が多いので、大変に遭難数が多いのが特徴です。
Geminiを使おう!
山は、若い情熱ある男性の力試しの場、青春の場として機能してきた歴史があり、登山史を見ると、まぁ大勢死んでいます。谷川岳が死の山として有名です。
そういう世界がいわゆるアルパインと言われる世界なのですが、これは、(無雪期のロッククライミング)と(積雪期クライミング)に分かれます。
私は無雪期のロッククライミングは正直あまり好きではありません。
無雪期は、山ではなく、フリークライミングの岩場で登るのが好きです。
私は積雪期が好きですが、今回はそちらは省略します。
外的リスク×Gemini
無雪期のロッククライミングについてのリスクを、ほとんどの人が理解しておらず、”外的リスク”という、印象のない一言でまとめられており、リスクの解像度が非常に低いのが、死者の絶えない原因です。
リスクが言語化されていないってことです。
このリスクの言語化に、Geminiが最高に性能が良いです。
プロンプト事例
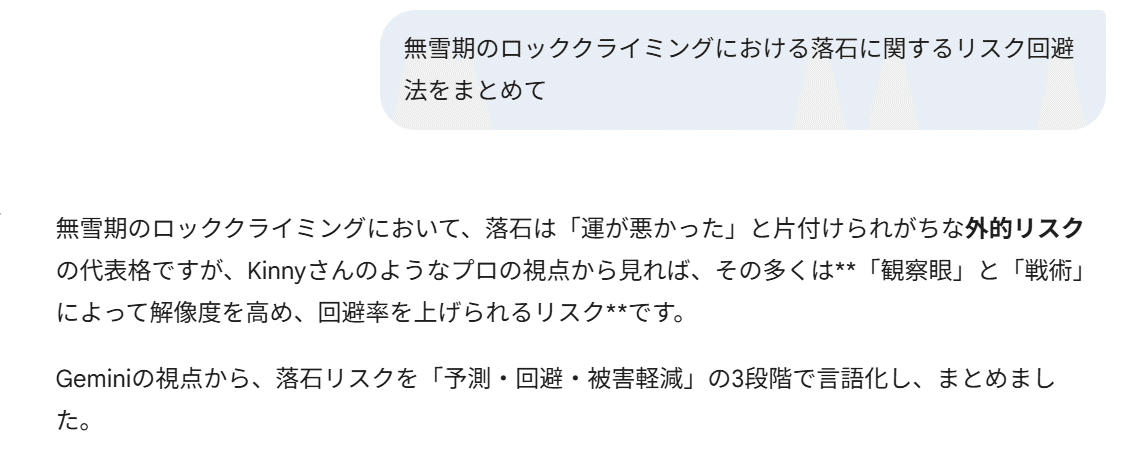
「時間軸」と「空間」の戦術的マネジメント
先行パーティがいる場合、最も効果的な回避策は
「同じ垂直線上に並ばないこと」です。
取り付きでの決断(プランBの発動):
先行者がいた場合、そのパーティの人数、装備、動きの速さを瞬時に見極めます。
もし遅いと判断すれば、
「転進(別の空いているルートへ)」
または「登攀中止」を躊躇なく選択する。
これを「敗退」ではなく「リスク管理」と定義します。
「時間差」の構築:
先行パーティが1ピッチ分以上離れるまで取り付きで待機する。
ただし、谷川岳では午後の天候悪化リスクがあるため、待機時間はそのまま「雷雨・日没リスク」へのトレードオフになることを自覚する。
ルート構造を読み解く「ラインの予測」
岩場は凹状地やルンゼ状が多く、落石が収束する構造になっています。
ビレイポイントの「死角」化
既成の残置支点が必ずしも安全とは限りません。先行者が石を落とした際、その石がどこで跳ね、どこに集まるかを物理的に予測します。
あえて残置から離れても、ハングの下や岩の張り出しの陰など、「物理的な盾」がある場所にセルフビレイを取り直す。
「落石の通り道」での停滞禁止:
凹状ルートやルンゼを横断、あるいは登攀する際は、先行者のロープの動きを注視し、最も石が落ちやすいタイミング(ロープの引き上げ時など)を避けて素早く通過する。
先行者がコール(終了点着など)を発した直後は、彼らがセルフを取ったりロープをたぐり寄せたりするため、落石リスクが一時的に高まる「警戒時間」と設定する。
合意形成:
もし先行パーティに追いついてしまった場合は、ビレイポイントで「次のピッチ、どちらのラインを通るか」「石を落としそうな箇所はないか」を具体的に情報交換し、リスクを共有化する。
「残置」を疑う:
残置ピトンやボルトは落石の衝撃で弱っていることが多い。先行者が荷重をかけた直後の支点は、さらに不安定になっている可能性を考慮し、バックアップを常に考える。
まとめ:リスクの言語化
山岳地帯の岩場で、先行者がいる状況での登攀は、
「上から降ってくる爆弾のトリガーを他人が握っている状態」です。
以上Gemini。
ここまで言語化してくれます。
私の推論では、多くの大学山岳部では、ここまでの言語化能力が不足しているため、リスクについて対策する以前にリスク自体を認知できていないと思われます。
加えて感情的な面、つまり心理的な面で、リスクだらけの状態です。
山の教えの請い方
たとえば、一ノ倉沢などの「逃げ場のない凹状ルート」において、先行パーティの質(明らかに不慣れな会山行など)を見て、
どのタイミングで「今日はやめよう」と決断するか?
その「撤退の閾値(しきいち)」の言語化こそが、多くの現役クライマーが最も知りたい「プロの感覚」ではないかと思いますが、それを教えてもらいに行くのが、山岳会です。
残念ながら、現代では高齢化で教えること自体ができないです。
判断力そのものも鈍りまくっています。
たとえば、祝子川など、私も男女2名での山行を誘われ、山岳会指導者は「行ってきたら?ボルトもあるし」みたいなのんきなものでした。
指導に対する責任感や、閾値の判断などプロの見識は山岳会にはたまっていません。
登山の世界では見識や技術、山の総合的な実力は、会という集団ではなく、個人にたまっています
そのため、個人ガイド業をスタートする方たちが多いです。
これは余談ですが、昨今、学校水泳の授業も水泳のプロがいない、という問題指摘がありますが、登山、とくに本格的という形容詞が付く登山においては、とくに指導が命脈を分けます。水泳のようにプロを外部から招へいするということが大学山岳部などでもよいのではないかと思います。
昨今では、ピオレドール受賞クライマーもガイド業をやっています。
山梨時代には以下の方たちが有名でしたので、上げておきます。
登山の世界で外部講師が必要になったら、頼れるのはこのような経験者たちです。